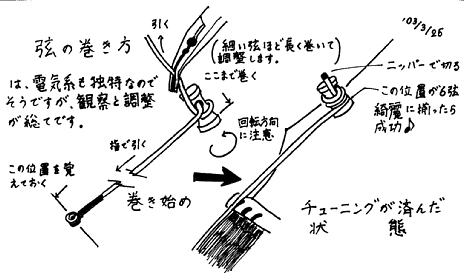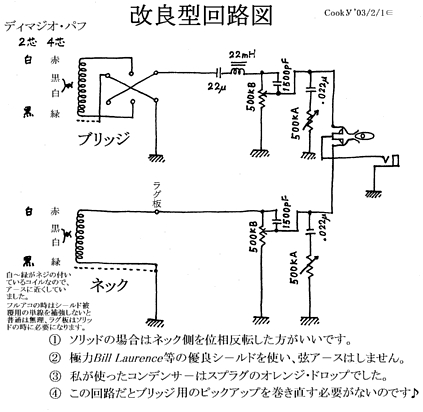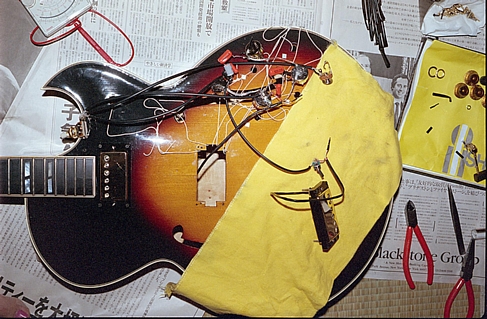|
Cooky Etsuco����́gGibson JAZZ
Guitar��Jim Hall�h�́@Guitar�̍\���Ɠd�C�n�҂�������֕��������Ă�����`��S(�[��)�m(��)�@�X�ɏڂ����Ȃ�\�肾�Ƃ��_? '
�D')/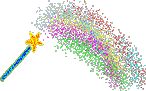 �`*���.'߁���::�.::-�c�E ��� �`*���.'߁���::�.::-�c�E ���
��Substance of The
Essay��
���ړ��Ă��ꗗ���Ă킩��^�C�g���\��������ɂ��t���܂������S(*�Lx�M*)�m
�����葁�������Ɓ@���̕��ɂ���@�G���N�g���b�N�E�M�^�[�t�҂����m��Ȃ��M�^�[�p�ꖞ�ڂ̕��͂̌��o���W�Ȃ̂ł�
���o���̐������y�|�W�����U���Ă��܂��̂͌����ɕs���ł����@�h�L�������g�E�t�@�C���`���ɂ��ē����摜�����L���Ă���̂Ł@�ړ����y���Ƃ������Ƃł��@���^�C�g���̊e���o���ւ͉E�͂��̎�����s���܂��@�ł́E�E�ق�(9/23�_
' �D'/�`*)���.'߁���::�.::-�c�E ���
���g�͂炷�h���߂�
�R������'01/2/23��
��Gibson's Catalogue��'02/6/10��
�� �S
����̎����'02/6/10��
�@�@�����A�|�X�̎�̎��ہ�'03/2/17��
���X�s�|�J�̊�b���_�E����蓶�b�`��
�ƋZ�p�`��'02/9/23��
��W���Y�E�M�^�|����̎��ہ�'04/1/17�`7/23��
�� �S ����̎����'02/6/10��
�S
:�@�u Cooky �Ɏ����`��I�S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
�S :�@�uJim
Hall�̊ۂ������������X�g���g�ŏo�����Ǝv������B
������Βʂ肾�Ǝv���E�E�B�A���v���Ń{�����[�����グ�āE�E�D�����e������E�E�E�v�B
�S
:�@�u��������('�D�O?�E�E�B�Ȃ����A�P�A�Q��
�������t�j�����ƁE�E�Ԃ̔��������ɂȂ���������`��S(�[�O�m�B
�F�B�ɕ�������AExtra
Light�������Ȃ��H�s�b�N�A�b�v�̖����āH�E�E�B
��('�D�O?�E�E�B�����ƁE�E�킩��ȁ`���I�S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
������-*��*-��-**��**-��-*��*-������-*��*-��-**��**-��-*��*-������
�y�{�f�B�̗v���́E�E�z
��܃W���E�z�|���̓��C�g�E�Q�B�W����B1����
9 ���炢�����ǁE�E�B
�{���́A�W���Y�������Ȃ��Ȃ�AFlat Wound��������
���������ǁAGibson��G-1040ML(�̂�040L)��1���� 11
�ɂȂ��Ă��܂����ė��R����ɂ����������m��Ȃ�(�O�O;)�B�^���E�t�@�|���E�̑����݂����ȉ��͎��ɃW���Y�炵�������Ă�����ˁ�
�֑��ɂȂ邯�ǁA�^���������̂́A�Ⴍ���������̑��߂� ������
�̏���A���炷�悤�Ƀs�b�N���g���Ă��邩��Ȃ�ˁ������Ă��ׂ����̕�������ł���Ă����`���|�L���O�p�̃s�b�N�ł����Ǝv���Ă���ƁA���E�����邯�ǁA�����d���ăs�b�N�̒e�͂��Ȃ��Ă��A�g����h���ɂ�����Α��ɂȂ���Ă��Ƃ������邩��ˁB�����ő����e����s�b�N�I�т́A���̐l�́g����h�ɂ����邯�ǁA�v�́A�g���̐l�������g�����������Ă݂Ĉ����|��Ȃ��s�b�N�������h���Ă��ƂɂȂ�́E�E�B������A�ގ���d���A�`��ɂ���Ă�1��1�Ⴄ����A�������~���̃s�b�N����ԁg�����|��Ȃ����H�h�́A���̐l���G���Ă݂Ȃ��ƈ�T�ɂ͌����Ȃ���(�O�O;)�B���ɁAFender���j�b�P������
9 �` 40 ���D��������'81�N�̃}�C�P���E�V�F���J�|�́A�n���R���i�C�����̃n�|�h���������AG-1040ML( 11 �` 51
)�������������́AJim
Dunlop��NYLON��.73MM���������ǁA�g����h����肾�����������H7������������1���̓M�^�|�ɂ��x�|�X�ɂ����x�����d����������B
�W���E�z�|���̘b�ɖ߂��āA
�}�C�N�̎�t���ʒu�����́A�t�����g�����ǂ��A���Ƃ��������ȏ��̃����E�}�C�N�B���̊J���ĂȂ��̐�ɔ����āA�J���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ�Ȃ���(�O�O;)�E�E�B�}�C�N��
6���̃l�W �͂���ƈ������߂Ȃ��ƃn�E��B
���ꂩ��A�u���b�W��Jazz
Guitar�̈�ԈႤ���ŁA�G�{�j�|�����|�Y�E�b�h�̖ƌ����Ă����B�g���h�T�E���h�z�|�� �f�U�C���̃A�|�`�h ���C�v���g�b�v
�t���A�R�|�X�e�B�b�N�{�f�B�Ƃ����d�l�� ES-175D
�Ƃ����M�^�|�����
�̂ɃM�^�|���ł͂��d�߂̉��F�ɂȂ��Ă�Ǝv���E�E�B������A���v���ŊÂ����Ă���炵����
�X�g���g�L���X�^-�̃V���O���R�C���͏o�������炵�ĊÂ��E�E�B�Œ�ł��n���o�b�J�|�̉�͗͂��Ȃ��Ɓg�R�V�h���E�����ڂ��邯�ǁA�t���Ă�H
�A���v�͊Â��ɐߓx������^��ǂ����g��Ȃ�����(�O�O;)�E�E�B�Ɍ��܂ŊÂ����Ă����܂肪�����B
�ȒP�ɏo������W���E�z�|���͑��݂��Ȃ���(��)�E�E�E�B
�W���E�z�|��
:�@�w����͂���(��)�B�o������̂��E�E�E�B�x�E�E�E(��)�B
2002/05/13������������������������������������������
�S
:�@�u ES175D �H
�s�b�N�A�b�v�����łȂ��A�}�C�N���}�E���g���Ă����('�D�O?�E�E�v�B
�S
:�@�u���p�̃��L�V�R�Y�t�F���_�[�̓t�����g����V���O���E�V���O���E�n���o�b�J�|�̏��ɂȂ��Ă��B���A�E�n���o�b�J�|�̓J���J���ɂȂ�̂Ŏg�������ƂȂ���B
�P�A�Q��
�ȊO�͂���Ȃ�ɋ߂����͋C�̉����o���E�E�B
�ł� 1�A2��
�͏o�Ȃ�(�[�O�E�E�B���A�ǂ����炢�����H�E�E�킩��ȁ`���I�S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
������-*��*-��-**��**-��-*��*-������-*��*-��-**��**-��-*��*-������
�y�\���ҁz
�͓̂d�C��ʂ��Ȃ��Ń��Y���E�M�^�|�Ɏg��������E�E�A�����t���ĂȂ��̂������Ă�����B�E�E�I�j�̓\�g(��)�B
���\���A�d�C�n���ɂ܂��g����m�ہh���Ă����Ă���g�Ⴂ�g�|���h�ɂ��Ȃ��ƁA�g�オ�Z���h�ꂿ�Ⴄ��(�O�O;)�B��
���̂Ȃ�Ibanez��
PM100BK ���߂������m��Ȃ��B�ق�A�W���E�z�|���ƈꏏ�ɂ���Ă���l��(��)�E�E�B
�\���b�h�ōČ�����̂Ȃ�H�t�����g��
�p�t
(�gPatent-Applied-For�h�B�{���͍����̂ŃR�s�B��)�����̃n���o�b�J�|�ƃ}�z�K�j�|�l�b�N�Ƃ̃R���r�l�B�V�������������Ȃ����
�X�g���g�L���X�^�|�͐������炵�ďオ�L�тȂ�����A�u���b�W�Ƀu���X���g���Ƃ����肪�����E�E�E�B
�y�d�C�n�ҁz
���ꂩ��A���̃s�b�N�A�b�v�Œቹ���o��p���|������ƌ��Ȃ��Ă���̂ŁE�E�A���]�i���g�E�s�|�N(���U���g���̒��S�B��ʓI�ɁA�����g�����O���āg��h���g���h�ɂȂ�悤�ɐݒ肳��Ă��܂�)�ɂ���邯�ǁE�E�A�P���Ƀg�|������������g��h���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���(�O�O;)�B
�����|=�f�B�}�W�I
�́A�w�s�b�N�A�b�v�̃T�E���h�́A�C���s�|�_���X�Ⓖ����R��背�]�i���g�E�s�|�N�ɑ傫���e�������B�x�ƌ����Ă����E�E�B
�����]�i���g�E�s�|�N����������ɂ́H���������Ȃ����Ď��͂�傫�������������̓C���_�N�^���X�ɊW�������āA�C���_�N�^���X�͒ቹ�ɊW�����邩�炾��E�E�B�R�C���Ɏ��E����p����ƌ𗬂��ʂ��Ȃ��āA���̒�R���C���s�|�_���X�ƌĂԂ�E�E�B��
�w���|�E�C���s�|�_���X�������x�ƌ����̂́A�C���s�|�_���X�������ƈʑ������傫������A�d���U����p���傫���Ȃ�̂ŁA�p���|�͏オ�邯�ǁA�傫�ȃG�l���M�|��K�v�Ƃ��鍂�����g���͗������炾��E�E�B�����āA�C���s�|�_���X�������ƁE�E�A�������ɂ���邯�ǁE�E�A�R�C���̖����������C���|�Ԃ̂�����Ƃ����ʑ����͕���ɉ��Z����邱�Ƃ������݂����ŁA����疳���̃L���p�V�^���X(�Ód�e��)����������ƁA�����Ɓg���h�܂ŃA�|�X����邱�ƂɂȂ�̂ŁA��������������Ȃ�ƌ����Ă����B
�܂�
�f�B�}�W�I �������������Ƃ�������̂́A�e�ʂ������Ȃ�����Ȋ��������ł��邩�炾�Ǝv��������Y�Z�p�I�ɂˁE�E�B�X���� �p�t���n
���ƌ������甃�����M�u�\���̃I���W�i���E�n���o�b�J�|(����������R�l 7.1�� �B�A���j�R5)�����A������R�������� 13.0K��
�������� �f�B�}�W�I �� X2-N
(�Z���~�b�N)�̕����s���������o�Ă�������ˁE�E�B�Z���~�b�N�E�}�O�l�b�g�̌��_���������Ō����ɃJ���@�|���Ă��܂����Ⴞ���(�O�O;)�B
�f�B�}�W�I
�� �p�t �Ȃ炱��ɍœK�Ȋ����ƃA���j�R5������邱�ƂɂȂ邩��A�S
�ɋ��_���Ă��ƂɂȂ��ˁ�(��)�B
��ʓI�ɂ́APassive(�d�r�s�v�̉�H�������܂��B���ʂ͂�����)�̏ꍇ�͒ቹ�̃p���|���Ȃ��Ȃ����Ⴄ���ǁA�p������(����)�ɔz��������E�E�A��a�}�O�l�b�g�E�X���b�O�̕��Ɋ�����ƃ��]�i���g��s�|�N�͍����Ȃ���
��A6500��
�Ƃ����g�����̃}�W�b�N�E�i���o�|�h�ɂ�������č̗p���Ă���A�_��=�A�|���X�g�����O �݂����Ȑl�������(��)�B�I�|���h�E�M�v�\����
�p�t�E�n���o�b�J�|
�ƃI�|���h�E�X�g���g�L���X�^�|�̃s�b�N�A�b�v�̃R�C���������Ă݂���A�����������������Ȃ̂����ċ��������āE�E�B
�_�� ��
�V�F�N�^�| �̂��߂ɐv���� �y+
�́A�o�|�E�}�O�l�b�g�̉��ɒ��ڃ��C���|���芪���Ŋ�������������B�{�r�����g��Ȃ����ڊ����́A�d���U����p�Ǝ��͂̊W�Ō����A������R��
10K��
�����邯�ǃ��]�i���g�E�s�|�N�̍����A�n���o�b�L���O�E�s�b�N�A�b�v�ł���Ȃ���p���`�����荂�����N���A�|�ȃT�E���h�ɍv�����ĂāA�}�O�l�b�g�Ɋւ��Ắu�A���j�R���Z���~�b�N�̕����ǂ��v�ƌ����Ă���Z���~�b�N�h(���͎͂ア��
�ێ��́�1500-2200�G���X�e�b�h
�͋����ł�)�Ȃ��ǁA����Ńo�����X���Ƃꂽ�v�����E�E�B
�g�n���h�E���C���f�B���O�h(�芪���ƌ����Ă��g���������@�h���g���܂��B�n����v����̂�'60�N�ォ��͐V�^�̎��������@�����y���܂���)�̑S�̓I�Ɋɂ��Ăނ炪���銪�����̓L���p�V�^���X�������Ŏ����Ȃ��E�E�B�����ł��Z���~�b�N�E�}�O�l�b�g�̌��_���g�����̃}�W�b�N�E�i���o�|�h�ŃJ���@�|���Ă��܂������ƂɂȂ��(�O�O;)�B
��PARACHUTE��
�� �� �̃p���`�̑��������̖��邢���́A���|�� �̃X�g���g�L���X�^�|�ɂ��� �V�F�N�^�| �� �^�b�v���s�b�N�A�b�v
���g���Ă�����ɁA�Ȃ��t���Ă����Ȃ����炵����(��)�E�E�B���� �Z�C���A=�_���J��
�̃X�g���g���AES-335TD�̂ɂ��ăX�|�p�|�E�n���o�b�J�|������Z���~�b�N�Ȃ��ǁA����Ɋ����������ɂȂ��Ă邻���B����('�D'
?)�B�ł��n���o�b�J�|�ɂȂ����ˁ�E�E�E�B
�W���E�z�|���̉��ɖ߂��āE�E�A���������Ⴂ�g�|�����t���t���ɂȂ�Ȃ��Œ������ɂ́A���������̗v�f�𗼗�������A�ƂĂ�����o�����X���o���K�v���Ă��Ƃ���(�O�O;)�E�E�B��������ɐ^����͖̂����Ȃ̂����ˁB
�^����ƌ����A�M�^�|�E�~���|�W�V�����̕]�Ƃ����̂́E�E�A
�E�@Active��
EMG
�̃A�^�b�N�ōő�3V�APassive�Ȃ珬���_���t���d����������Ȃ����ɁA�M�u�\���A�t�F�_�|�ɕ���ĉƒ�p�̒�i125V�̑傫���X�C�b�`�ނ��g���̂������Ǝv���Ă�����A
�E�@�E�E���Ǝv���A���{�̃I�|�f�B�I�p�{�����|���Ȃ琢�E��Ȃ̂ɁA���₷��CTS����A�����Ɖ��₷�����Y�̊y��p�̃R�s�B�̕��������Ǝv���Ă�����A
�E�@���Ⴀ���������̂��H�Ǝv���A���̙{���ʂ�
�Z�C���A=�_���J�� �ł����AJAZZ
BASS�AP-BASS�V���|�Y�̃��|�h����BASS�ňꉞ�n���E�L�����Z�������炩�H�V�|���h�ɂ��ĂȂ��āA�m�C�Y���W�|�W�|���Ă���̂�����Ă����肷�����E�E�A�������炯�����(�O�O;)�B
����Ȃ����ς͈�U����������(��)�A�g�{���͎c���Ȃ���Ⴂ�g�|���ɂȂ�����H�h�������ǂ��H����Ȃ�ł����˄�('�D'
?)��(��)�E�E�E�B
�S
:�@�u�ł��Ȃ��悧�����S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
2002/05/14������������������������������
�S
:�@�u���������̂��Z�~�A�R���Č�����('�D�O?�B�E�E Cooky
�̓E�`�H(��)�B
�����e���Ă����ɂ́A�\���A�d�C�n�`���v���J���v���E�E�E�B
������-*��*-��-**��**-��-*��*-������-*��*-��-**��**-��-*��*-������
�y�n�C�����h�~�@�z
�̂Ȃ���̋ɂȂ��Ă�����̂��t���A�R�|�X�e�B�b�N�A�n�E�h�~�̃u���b�N����ꂽ���̂��Z�~�A�R�|�X�e�B�b�N�ƌ�����(�O�O;)�B�E�E�I�j�̓\�g(��)�B
�@�@�ʏ�Ƃ͋t�́A�x�|�X�E�g�|���E�R���g���|�������ɂ́A�{�����|���E�|�b�g���g���ăR���f���T�|��ʂ��ʂ��ς��邩�H�{�����|���E�|�b�g���g���ă`���|�N�E�R�C�����A�|�X��������E�E�B�`���|�N�E�R�C���̓������C���_�N�^���X������A�`���|�N�E�R�C���͒ቹ��ʂ������������B
�A�@���A�e���L���X�^�|�̃{�����|���E�|�b�g�ɂ́A���͂Əo�͂̊Ԃ�
0.001��f(1000pF) �̃R���f���T�|���t���Ă����B��������{�����|���������Ă�(��R�������Ă�)�A0.001��f
��ʉ߂��邱�Ƃ��ł��鍂�������͊m�ۂ���邩�炾��E�E�B�����Ɓg���h�܂Œʂ��������̓L���p�V�^���X��傫�������B
�B�@�N���|�}�|
�ł̓g�|���E�R���g���|����ʏ�Ƃ͋t�́A�{�����|���E�R���g���|���̏o��(�|�b�g�̒���)�Ɍq���Ńn�C�������ɗ͖h���ł������
�C�@��̃s�|�N��ݒ肷��̂́A�g
LC�l�b�g���|�N �h�ƌĂ��p�b�V����H���g���AQ�o���h(�t�B���^�|�̉e�����y�Ԏ��g���т̕�)���������L�����ȒP�ɂł�����E�E�B
L �̓`���|�N�E�R�C���̓����̃C���_�N�^���X�AC
�̓R���f���T�|�̓����̃L���p�V�^���X�̂��Ƃ���B
�����3�E�F�C�E�X�s�|�J�ȂǂŎ��g���т�3�ɕ�����̂ɂ��p�����A�v�Z����
�@�@�@�@�@�@�@
1
L���\�\�\�\�\�\�\�\
�@�@�@ (2��F)2��~C
L �̓C���_�N�^���X�ŒP�ʂ̓w�����|(H)�A
��
�͉~������3.146�A
F �͊�]������g���т̒��S���g���A
C
�̓L���p�V�^�|�̗e�ʂŒP�ʂ̓t�@���b�h(f)�B
���@0.1mf (���{�ł� 0.1��f )�� 0.0000001f
����(��)�B
�M�^�|���ƁA22��f ( 0.000022f )�� 22mH ( 0.022H )�ŁA�s�|�N
228.4486547Hz ���g��������('�D'
?)�E�E�B
�R���f���T�|�ƃ`���|�N�E�R�C�����V���|�Y(����)�ɔz�����邾���Ȃ̂ŁA������s�b�N�A�b�v�ƃ{�����|���E�|�b�g�̊Ԃɓ����Ί��������E�E�B�킩�����H
�S
:�@�u�v�Z�ł��Ȃ��悧�����S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
2002/05/18����������������������������������
�S
:�@�u������ �p�t �ɂ́A�ǂ����ăJ�o�|���t���Ă����̄�('�D�O?�B
�f�B�}�W�I �� �p�t
�ɍi���Ă���ނ��������āE�E�A�ǂ�ɂ����炢�����H�E�E�킩��ȁ`���I�S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B
������-*��*-��-**��**-��-*��*-������-*��*-��-**��**-��-*��*-������
�y�ł��邾���I���W�i���z
DiMarzio
��
PAF �A
PAF 7 - New �A
PAF Pro �A
PAF Classic Neck
�A
PAF Classic Bridge
�̒��������� PAF Classic Neck ���������E�E�B PAF
�Ƀj�b�P���E�V���o�|���̃J�o�|��t���Ă��������Ƃ���B
���݂ł́A�p���|�������ł��グ�悤�Ƃ��ăJ�o�|���O�����ǁA�w�r���^�łȂ�����(��)�A���E�̕����L���N���A�|�ȃT�E���h�ɂȂ��������������炾��B
EMG
(�I�|�o�|�����h)�ł͓��Ɏ��E�̕����L�����邱�ƂŁAEMG-�n���o�b�J�|
���A�u�N���A�|�Ȃ�����p���t���ȃT�E���h�v�ƕ]�����A�~���|�W�V�����̖]�ރT�E���h�Ɏd���Ă邱�Ƃɐ������Ă�����E�E�B�������A�M�^�|�E�~���|�W�V�������A
�E�@�u���E���ɓ����R�C���͈̔͂��L������ƃp���t���ȃT�E���h�ɂȂ�v�Ǝv���Ă���͔̂������������Ă��Ȃ��āE�E�A���E�̕����ׂ��C���|�W���炻���v���Ă���A
�E�@�u�N���A�|�ȃT�E���h�Ɣ�����ȃT�E���h�������Ă���v�ƁA
�E�@�u�V���O���R�C���E�r�b�N�A�b�v�̕������悪�����B�����R�|�h���|�N�ʼn������ڂ��Ȃ��B�G�t�F�N�^�|�̃m�����ǂ��v�ƁA
�E�@�u�Z�p�|�|���s�|�X�Ŏ��������������Č��ɓ��Ă������p���t���v
�Ɩ������Ă����(��)�B
���E�̕����L����Ό��U���̊��m�������ɂȂ�̂ŁA�C���|�W���͂����ƃN���A�|�ɂȂ����ŁE�E�A�C���_�N�^���X�Ǝ��͂̊W�������W�����C�h�ɂ����邩��A���܂ŏE��Ȃ������d�ቹ���������������ɂ͂Ȃ邯��ǁA�����p���t���ł������́g�R�V�h�ɑ�������p���`�̗v�f�������āA�����������C�h���̓p���`���Č���Ȃ����炾��(�O�O;)�B
EMG
���ŏI�I�Ɂg�N���A�|�Ȃ�����p���t���ȃT�E���h�h�ɂł����̂ɁE�E�A���E�̕��̍L����������Ȃ����āE�E�A�o���g���|�j
�ƕ���Active(�v���A���v�����Ɠ��`�ł�)�����ӂȃ��|�J�|�Ȃ̂ŁA���߂�������Ńo�����X���Ƃ��悤�ɃR�C���ƃA���v��V�v�������ƂŁA�ቹ�܂Ń^�C�g�ɏE����p���`���o�����e�����傫���Ǝv����
���݂ɁA���̃A�N�e�B����H���Ȃ��A(������̃p�b�V�������ʂł�)�A�Z�C���A=�_���J��
�� �N�E�H�|�^�|�E�p�E���h (�t�F���_�|�̃V���O���R�C���́A6�̃}�O�l�b�g�E�X���b�O
�̉��Ƀ��C���|���������\���ɂȂ��Ă��܂����A���̃X���b�O�̒��a��4����1�C���`�Ɋg���������̂ł�)�̂Ɋ������ꍇ�́E�E�A�}�O�l�b�g�̓A���j�R5(
���́�12500�K�E�X
�͍ł������ł�)�B�}�O�l�b�g�ɗ͂�����̂Ń��]�i���g�E�s�|�N���オ���āA�T�X�e�B���̔����ȐU���܂ŕ�����j���A���X�͊Ô��Ń����E�ȃr���e�C�W�E�T�E���h�Ɠ��������ǁA��a�}�O�l�b�g�E�X���b�O�͎����̕ω�����芊�炩�ɂȂ邽�߁A���̗֊s���͂����肵�ė��ăN���A�|�ɂȂ����ŁE�E�A���E�̕����L���̂��n�|�v�Ɏ������s���������o����̂��H���݁A�[�݂����������F�ɂȂ������ǁA�p���`�͗]�芴�����Ȃ�������(�O�O;)�B
�E�C���A��=�o���g���|�j
�͂������������̕ω��ƃG���N�g���j�N�X�ɂ͓��ɏڂ����A1980�N�ɂ�30�ȏ�̓�����������l�ŁA�o���g���|�j �� 6���s�b�N�A�b�v
�ƃv���A���v�����s�b�N�A�b�v�͗L�������E�E�BJAZZ�̔��W���肤����Ƃ��ẮA6���ʁX��
�f�B�X�g�|�V�����������āA(KT77�AKT88�Ȃǂ̍������p�����^��ǂ́A�o�͒i�̃I�|���@�E�h���C���܂� 6ch
�ɕ����Ă����̂����z�ł�)�A6 Part
�Ɨ����č���������ŏI�I�Ƀn�|���j�B�Ƀ~�b�N�X����A�g���x�ȃR�|�h�h���g���Ă�����Ȃ��͂����Ǝv���Ă���̂ŁA6���s�b�N�A�b�v
�̂悤�Ȕ��z�͑傢�Ɋ��҂������Ƃ��낾��E�E�B���b�h=���|�Y�v�̃x���x�b�g�E�n�}�|�̃U�E�X�e���I�E�s�b�N�A�b�v�� 6���Ɨ��R�C��
�̂悤�ɁA1�A3�A5����2�A4�A6����2�ɂ܂Ƃ߂ďo�͂��Ă���������̂ŁA����4�{�w�ł�����(��)�A�W���E�z�|���̎g�p�����悭��������
4 Part
�o�͂Ƀ��|�h������������ƁA���������ł͂Ȃ����y�I�ɂ����p�I�Ȃ��̂ɂȂ���E�E�B
�����A�o���g���|�j�́u�}�O�l�b�g��R�A�̍ގ��̓T�E���h�ɑ傫���e�����Ȃ��v���Č����Ă�A�����̃O�@���l���Ɏ����\����`�҂Ȃ��(��)�E�E�B�ł��O�@���l���������������悤�ɁA��������
Trial and Error�����s���� ���o���l���A�ォ�炢���ޗ����g���悤�ɂȂ�� �S �ɋ��_�Ȃ��(��)�B
�����I����
�S �͂���̐���M����́H�I
�S
:�@�u������(�[�O�E�E�B�g��������Ă����������h�����Ȃ̐搶�́E�E�l�C�����������ǁE�E�A���Ƃ����玩���őI���ł��Ȃ�����������`��S(�[�O�m�B�v�E�E�E(��)�B�܁�
2002/05/19����������������������������������������������
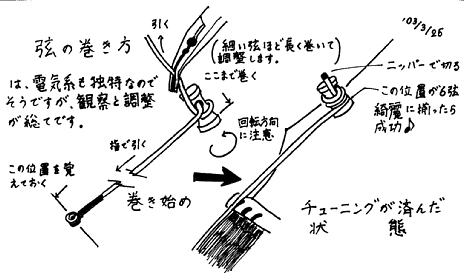
|
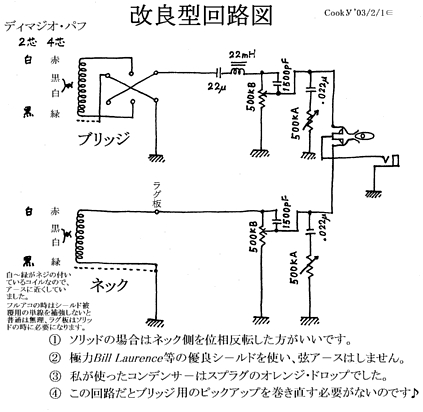
|
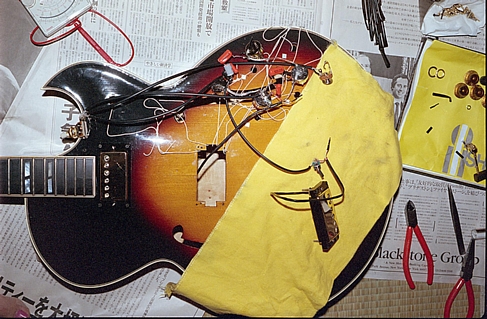
|
����16�N�o�������_�ŁA���̊y��̓d�C�n�̓{���{���Ńs�b�N�A�b�v�������Ă͎g�����ɂȂ�܂���ł����B�y��{�̖̂ؕ��̓s�b�N�A�b�v�̌����J���Ė���čw�������̂�29�N�ȏ�o���Ă��܂����A�S�R�����������ł���
���A�|�X�̎�̎��ہ�'03/2/17��
�S
:�@�u�ǂ����Ă����ƐV�����ł��Ȃ���('�D' �O?�v�B
Cooky
:�@�w�v�����g����̗p���Ă������ɐV�����Ƃ͉��̊W���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾��x�B
�S :�@�u�����H�ǂ�����('�D'
�O?�E�E�v�B
Cooky
:�@�w�����āA�|�b�g�̎������l������v�����g��Ղ��Ǝ̂Ă邵���Ȃ�����Ȃ��H�|�b�g�A�X�C�b�`�A�W���b�N�P�̂̎G��������p�I�ɂ���C���Ȃ��̂ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ���(�O�O;)�x�B
�S
:�@�u���p�I���āH�E�E�v�B
Cooky :�@�w��ׂ���I�|�f�B�I�p�̃|�b�g�AVIOLET
N-245�̕����������̂ˁB�����̕����ǂ�����(�O�O;)�B�����M�U�M�U�ɂȂ����V���t�g�ő��点�Ă��A�y��p�̃|�b�g�����ʕ����������₷����ˁE�E�B���ɂ��A�|�b�g�̋����P�|�X�̏�ɐe�A�|�X�����{�������Ȃ��āA���̏ꍇ�ɏɎ_����y�|�X�g���g�����Ƃ��d�C�n�̎������k�߂���Č����������x�B
(�y��p�ɓK���Ă���̂̓M�U�M�U�ɂȂ����V���t�g��\�������A���ɏo��g�y���h�ł��B�M�U�M�U�ɂȂ����V���t�g�������߂�A�܂�m�u���l�W�~�ߎ�����I�ׂA�g�ϋv���\�h�̑f���炵���|�b�g�����ł��g����悤�ɂȂ�܂��B�A���A����̃��X�E�|�|���E�S�|���h�E�g�b�v��Gold
Top Hat or
Bell�m�u�́A�M�U�M�U�ɂȂ����V���t�g�p�ł����B�����ăM�U�M�U�ɂȂ����V���t�g�̃|�b�g�́A�I�|�f�B�I�p�ł������̈����������ł��B�����������ŁA���̃I�|�f�B�I�p�̃|�b�g�AVIOLET������AMBER��Gold
Top Hat or
Bell�m�u���t�����A�y�ʂŃ��b�L���������Ƃ����O���q�������Ă������߁A���̃|�b�g�ɂȂ�܂����E�E�B������'04�N��12���ɁA�v���U��ɂ��̃|�b�g���������H�t��RADIO
STORE�̓����֍s���Ă݂�ƁA���ɓX���ɂ͂���܂���ł����B�����ł� A�J�|��
�͋H�����������̃|�b�g���A�Z�܂������v���Ȃ��Đ��Y����Ȃ��ƂȂ�ƁA���̎���Gold Top Hat or
Bell�m�u�̕����l�W�~�߂ɍ�芷���A�g�y�ڂ̑ϋv���\�̑f���炵���h�|�b�g��{�����������������m��܂���)�B
�w�n���_�͐�ɉ��M���Ă��镪�����n���Ȃ����ǁA�u�ԏ����Ȃ�40W�ŏ\���̎��ɂł��邾�������Ŋ����Ŋ��Ⴂ���x�ŗn����(Sn62���ȏ��)���j����n���_(���W������n���_)���W���b�I�R���f���T�|�����j���ŕی삷��(�M���܂�)�ɂ��Ă��A�n���_�̗ʂ����Ȃ����������Ă��Ƃ͌������(��)�E�E�E�x�B
�S
:�@�u�\���b�h�̏ꍇ�ɃR���g���|���E�L���r�e�B�ɓ`�����h����h���āA������V���V�B�̑��ɂ��Ă���V�|���h���@�����������ǁA���������炾�߂Ȃ́H�v
Cooky
:�@�w���O�̌o�H���m�ۂ��Ȃ��Ń|�b�g�̋����P�|�X���g���K������ς��Ȃ��ƁA�ǂ������A�e�A�|�X�����|�b�g�̋����P�|�X�̏�Ɂ����`�Ƀn���_�t�������̂Ȃ�A�Ӗ����Ȃ��Ȃ����ǂ�(�O�O;)�E�E�B��������APARTS�P�̂�
�����ȃV�|���h
��ڍ����������ǁA�����ʂŃV�|���h���ꂽ�y��p�̃W���b�N���������ƂȂ����̂ˁB����ł�����������Č��A�|�X�����͂��Ă����A���y���Ȃ�PARTS�͐V�����Ȃ�Ȃ���Ȃ�ˁE�E�E�x�B
�S
:�@�u���͉�H�}�ɏ����ĂȂ��A�|�X�̎���Ă킩��ȁ`����('�D�O;���v�B
Cooky
:�@�w�{�����|���E�R���g���|�������āA�|�b�g�̏�[�Ƀ}�C�N�o�͂������āA�����̃��C�p�|(�u���V)������o���܂ł̒�R�����l���Ȃ��ƁA�e���̏ꍇ��1M���̒�R�l����ꂽ�̂ł̓p���|�����ʂɂȂ�悤�Ɏv���Ă��܂����ǁA�{�b�g�̉��[�̓A�|�X�Ɍq�����Ă������t�ł���('�D'
?)�B�A�|�X�Ƃ̋����̓C���_�N�^���X�ɊW�������āA���̏�[�����[�̒�R�l�̓s�b�N�A�b�v�ƕ���ɓ����đS�̂̃C���_�N�^���X�������Ă��邩��A��R�l���Ⴂ�ƁA�e���̂悤�ȍׂ������X�ɍׂ��Ȃ��ˁB���A���̂��I��Ȃ��ڑ�����Ă��邱�Ƃ���H�ƌ����A��Ă����特�o�Ȃ���(�O�O;)�B
�S �́g����g��H��1�_�A�|�X�h���Ēm��Ȃ��H��(�K���P �O?�_('�D' ?)�E�E�x�B
�y ES-175D
���A���X�E�|�|�����̏ꍇ�́g1�_�A�|�X�h�z
��܃|�b�g�A�X�C�b�`�A�W���b�N�̋����P�|�X�ւ͉�H�}�ɏ����ĂȂ��Ă��A�|�X���킹�܂��B�V���V�B�Ɏ��t���Ă����ł͂Ȃ�����ł��B�������āA�\�Ȍ���g��{�h�̃A�|�X�����g�߂��h�A�|�X���Ŗԗ�����悤�ɁA�V�|���h�핢���A�|�X���Ɋ܂߂đ����I�Ɏ�����߁A�V���V�B�ւ͂��̐e�A�|�X�����g1�_�A�|�X�h����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�V���V�B�ւ�2�_�A�|�X�A�܂�w�A�|�X�����ւɂȂ��Ă���ƃn�����E���₷���x�ƌ����Ă��܂��B
�Ⴆ�A�g�O���E�X�C�b�`����|�b�g�֍s��2�{�̃V�|���h�핢�̓��A�������q���ł��܂������́A�e�A�|�X���ƃ��|�v�ɂȂ��Ă���͂��ł�(�O�O;)�B�����ł͉��̃{�����|���E�|�b�g�����g�߂��h�A�|�X���ɂȂ�悤�Ɏc���A����1�{�̃V�|���h�핢��Г��ɂ��܂��������A4�̃|�b�g�����Ԑe�A�|�X���������`�ɂȂ�̂́A�����ł̓e�C���s�|�X�֍s�������g��{�h�̃A�|�X���ɂȂ邽�߂�������ł��ˁE�E�B���́����猷�A�|�X������Ă��܂��Ɓ��̕����g��{�h�ɂł���悤�ɂ��v���ė��܂����A���̕�������ς��̃{�����|���E�|�b�g���~�j�E�X�C�b�`���V�|���h�E�v���|�g�ցg��{�h�ōs���₷���̂ŁA�ŏ��Ɂ��ɂ����l�Ƃ����͎̂��ɐ�̉��p��܂ōl���Ă����̂ł���(��)�E�E�E�B
������-*��*-��-**��**-��-*��*-������-*��*-��-**��**-��-*��*-������
�S
:�@�u�m��Ȃ�����(��)�E�E�E�v�B
Cooky
:�@�w���炱��(�O�O;)�E�E�B�t���A�R�̎��̓A�|�X�p�Ґ��łȂ��Ɩ����A�~�j�E�X�C�b�`�̌��ւ͎����b�L�����̒P����ʂ��܂��傤�B���A�|�X�͂��Ȃ����ǁA�����m�u�ɂ͉��r�`���|�u���Ԍ˂̃S���E�p�b�L���O��킹��Ƃ�����B���ꂩ��E�E�A�W���b�N�A�g�O���E�X�C�b�`�ւ̃A�|�X�ƃs�b�N�A�b�v�̍��E����Q���ăn���_�t�����������o���̐��́A�M�ŏk�ރ`���|�u�Ő≏������A�|�X�p���O�[�q�̕t�����|�b�g�Ƃ��A�}�U�|�{�|�h�̂悤�ȍ����ݎ��Ƃ��A�����܂Ŏ��p�I��PARTS�����y��������������V���邩���m��Ȃ����ǂ�(��)�E�E�B�킩�����H�_('�D'
?)�E�E�x�B
�S
:�@�u���̂��E�E�B���A�|�X���ĉ��ł���H���Ȃ��Ă��C�ɂȂ�(��)�E�E�B���ꂩ��A���ɏ]���ƃ|�b�g�̑I��͂ǂ��Ȃ��ł����('�D'
�O?�v�B
Cooky
:�@�w���A�[�X�Ƃ����̂͌����A�|�X���Ă����ł͂Ȃ����āA�X�e�B�W�ł́g���t�҂��A�|�X��G���Ă���Ɓh�A�m�C�Y���ȒP�ɎՒf�ł���Ƃ������̂�����A�g�l�̃A�|�X�h�����(�O�O;)�B����́A�d�M���̓d�������ǂ��炩������A�|�X����Ă�����ǁA���̃A�|�X�ɉ��t�҂̑̂�`������d�C���߂��قǂ����Ȃ�́B������A�d���v���O�������ދɐ��ɂ���Ă��m�C�Y�̑������Ȃ��������B
�͓̂d����H�̃g�����X���Ȃ����g�����X���X�����̃A���v�������āA�ڒn���ɂȂ��Ă��Ȃ��V���V�B��G��Ɗ��d��������A�v���O�������ތ����ɂ͑傢�ɐ_�o���g������(�O�O;)�E�E�B�����Ƃ��A�����C������������`������d�C�Ȃ̂ŁA100V�ł͂Ȃ��������ǂˁB
Vocal�p�}�C�N�̃A���v�ɂ��g�����X���X�������āA���̋ɐ����M�^�|�ƍ����Ă��Ȃ��Ɣߌ��͋N��E�E�B�Ⴆ�A����̓m�C�Y�̏��Ȃ����̋ɐ��ɂ����A�M�^�|�̌��������Ă��邩��A���Ƀ}�C�N�͉E���L���Ĉ��낤�Ƃ��邶��Ȃ��H�Z�b�e�B���O�̎�Ⴂ�ŋɐ����قȂ��Ă����ꍇ�A�ق�I����100V�����聨�S�����E�����C�ɋ삯�����邱�ƂɂȂ��I240V�d�����g�p����C�M���X�����Ȃł́A�m���ɓV���̏Z�l�ɂȂ��Ă��(�O�O;)�B
���́A�s�b�N�A�b�v�E�J�o�|��u���X�E�s�b�N�K�|�h��G��A���A�|�X�������̂Ɠ������Ƃ����ǁE�E�A������́A�E��̃}�C�N�Ɨ����G��\�����w�ǂȂ������A���S�Ȗ���ˁB
�Ⴆ�A�p���Captain�ƌ�������A���ꂪ�D�����͒����@�����ē��������叫��(�w����)�g�����������H��(��)�A���������Ď����őz�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ˁE�E�B�ł������s���Ƃ������Ƃ́A���������悤�Ƃ��邱�ƂŋN��Ȃ��Ȃ邶��Ȃ��H
�������g�����̐l�͌��ꂪ���S�Ȃ�C������������A�g���̃A�|�X���h�A�g���������A�|�X�����Ȃ����̂��������ȁh�Ɖ��߂��Ă��܂����ǁA���̌����Ƃ͋t�̔��f���A����l���ŋ����Ǝv���Ă���
�^���̔���
�́A�ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ���(�O�O;)�E�E�B�ߌ��ɂƂ��Ēv���I�Ȃ̂́A�z���͂̌��@��������B
��������A���ЃA���v�Ƃ̑g�����܂ōl���Ă��Ȃ��g���A�|�X�́A�ǂ�ȗL���y��X�����߂Ă����Ȃ��Ă����h���Č����Ă��x�B��
�S
:�@�u�s�F�`���S(���[���O�m�B�|���̂͂悭�킩��܂����v�B
Cooky
:�@�w�|�b�g�̑I��́A���̊J�����̂͂�������m�C�Y�������B�ق�Ƃ́A�V�|���h�̕Ґ�������������ʂ̒��ɓ��ꂽ��ŁA���A�|�X�̂��Ƃ��l����̂���Ԃ�������A���A�|�X�ɔ����Ă����ł͂Ȃ����ǂˁE�E�B���v���ɏグ�����t�߂��悭�g���̂Ȃ�|�b�g��
B (���C�i�|�E�^�b�p�|�E�|�b�g)�A���ɁA�����v���ɍi������t�߂̔��������K�v�Ɗ��������̓|�b�g�� A
(�I�|�f�B�I�E�^�b�p�|�E�|�b�g)�ˁ�y��̎��̓V���t�g�����悭�g���ʒu�ł̃J�|���̊ɂ₩���őI�肷���x�B
�S
:�@�u��R�l�̓�('�D�P�O?�E�E�v�B
Cooky
:�@�w������������J�|���Ȃ͓̂�����(��)�B�{�����|���E�R���g���|���̒�R�l�̓p���|�����ʂɂȂ�Ȃ����ė��R��1M�������s�肾���ǁA����ƃs�b�N�A�b�v�ɂ���Ă͕ω������}�߂���̂ˁB�����Ŏ��͂���ς�500K����
B �ɗ��������AA ���D����Gibson��500K���� A ��300K���� A �ɂȂ����E�E�B�ق�I�����ł���H�_('�D'
?)�x�B
�S :�@�u��(~�D�P�O)�yZZ������zzzz�ǂ����ł���H�E�E�E�E�E�v�B
Cooky
:�@�w���߂�����ჰ=(*�K���P�O�_('�D'
?)�B�x�E�E�E(��)�B�܁� | 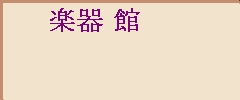
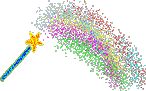 �`*���.'߁���::�.::-�c�E ���
�`*���.'߁���::�.::-�c�E ���