Cooky Etsucoさんの“Gibson
JAZZ GuitarでJim
Hall”の Guitarの構造と電気系編をこちらへ分けたんだってうっわ~んヾ(δーδ)ノ(笑) 更に詳しくなる予定だとか\?
' .')/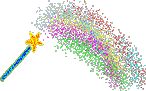 ~*☆。.'゚★。、::。.::-…・ ・☆ ~*☆。.'゚★。、::。.::-…・ ・☆
ΨSubstance of The Essay♪Ψ
お目当てが一覧してわかるタイトル表をこちらにも付けましたぁヾ(*´x`*)ノ
手っ取り早く言うと 下の方にある エレクトリック・ギター奏者しか知らないギター用語満載の文章の見出し集なのです
見出しの数だけペ-ジが分散してしまうのは検索に不利ですが ドキュメント・ファイル形式にして同じ画像を共有しているので 移動が軽いということです 他タイトルの各見出しへは右はしの耳から行けます では・・ほい(9/23\
' .'/~*)☆。.'゚★。、::。.::-…・
・☆
<“枯らす”ための コラム>'01/2/23∈
<Gibson's Catalogue>'02/6/10∈
< 鬼 からの質問状>'02/6/10∈
┗<ア-スの取回しの実際>'03/2/17∈
<スピ-カの基礎理論・肩代り童話~癖
と技術~>'02/9/23∈
≪ジャズ・ギタ-入手の実際≫'04/1/17~7/23∈
<Gibson's
Catalogue>'02/6/10∈
♪⌒1974年に神田商会が作った Gibson-∈PIPHON∈
総合カタログ から、
BanjoのRB-100、RB-250、RB-350を除いた
NECK SPECIFICATIONS : マホガニ-
セットネック
の全機種を抜き出してみますと、次のようになります♪
∴ ∈PIPHON∈ にマホガニ-ネックのものはありません。
LES PAUL CUSTOM ⇒ メイプルトップ ソリッド
マホガニ-ボディ
エボニ-指板
LES PAUL DELUXE ⇒ メイプルトップ ソリッド
マホガニ-ボディ
ロ-ズウッド指板
ES-150DC ⇒ ア-チド
メイプルトップ ア-チド メイプルバック
ロ-ズウッド指板
ES-175D ⇒ ア-チド
メイプルトップ ア-チド メイプルバック
ロ-ズウッド指板
LES PAUL TRIUMPH ⇒ ソリッド
マホガニ-ボディ
ロ-ズウッド指板
LES PAUL RECORDING ⇒ ソリッド
マホガニ-ボディ
ロ-ズウッド指板
SG SPECIAL ⇒ ソリッド
マホガニ-ボディ
ロ-ズウッド指板
SG STANDARD ⇒ ソリッド
マホガニ-ボディ
エボニ-指板
SG CUSTOM ⇒ ソリッド
マホガニ-ボディ
エボニ-指板
‡§‡-***-∽-*****-∽-***-‡§‡-***-∽-*****-∽-***-‡§‡
【マホガニ-ネック】
マホガニ-ネックは、これまでの常識のメイプルネックに代って、レス・ポ-ル属の成功から、“f”サウンドホ-ル
デザインのア-チドトップ
フルアコ-スティックボディにまでフィ-ドバックするようになった素材です。それはフロントにつけた、パフ
(“Patent-Applied-For”。 ビンティジ・パフ
は1955年-1960年代初期にかけて製造され、数百ドルの値がついているのでコピィ可)推奨のハムバッカ-とのコンビネィションにおいて、“音を粘らせ枯れた音にする”要でした♪
マホガニ-ネックには安い(笑)ロ-ズウッド指板を貼った方が、アタック部分の粒が丸くなり、サスティン部分との繋がりもスム-スになるようです。この、サスティンではないが伸びる部分を“コシ”と言い、“枯れる成分”は正にここに含まれていると考えられます・・。
サスティンでは一転して低いト-ンの“枯れない音”になりますが、ギタ-ではその“コシを引っ張って持続させる作用”もしているため、サスティンだけ切る訳に行かないのです(^^;)。
そこで、まだ“コシへの理解者が多かった”当時は、“コシが長くて、サスティンが収束しやすい”素材を独自に捜すことになったのでしょう・・。それはマホガニ-ネックにしたらとてもバランスのいい減衰曲線が得られました♪
アナログが終ろうとしていた1981年の録音で、REOスピ-ドワゴンのゲイリ-・リチラ-スが弾いていた
ギブソン・レスポ-ル・スタンダ-ド'60年
(♯02186と♯01939)
は、武道館という容積に対してMarshall・50wのパワ-管が、(
6CA7=KT77=EL34 2本のプッシュプル動作で50Wとするぐらいが、大きい真空管で“下”が締まって来る中では“上”も途切れない音になって丁度いい。当時マイケル・シェンカ-も同じ意見だった♪真空管の場合、パワ-管にはこだわるが、できるだけ出力段に近いオ-ヴァ・ドライヴの方がマイルドだと言う)、適度にヴァイオリンの弓のような作用をした結果とは言え、蕩けるようにクリア-なアタックが“甘露な露の一滴”を思わせ、甘美でメロウな余韻は会場の隅々で、如雨露となって降り注ぎます・・。
所変って、2000年に徳永 二男のストラディヴァリを生の音で聴いた時の印象は、実にプリプリした艶っぽい音が会場に発せられ、イタリアの明るいフル-トが空から柔らかい日差しとなって降り注ぐので、私は天井を見ていました♪・・。その時、“歴史は移りギタ-になっても、名器の条件は同じになる所が凄いな”と思いました・・・。
【ヴァイオリンの名器】
スティ-ヴン・マルキオ-ネは『ギブソンのギタ-はそのル-ツを、ドイツ系ヴァイオリンにまで辿ることができる。』と言っています。
そのドイツのカ-ル・シュタイナ-(、G弦はオ-ボエのような音が出せる多彩な楽器という評でした。)とパガニ-ニの愛器イタリアのグァルネリ、(稲妻のようなパッセ-ジを奏でたという彼の愛器には、“カノン砲”という銘がついていました)、そして同じくイタリアの純度の高い明るい空を思わせるストラディヴァリの個性も、その“コシ”の持続とサスティンのミュ-トという相反する二つの要素を極限までバランスして行く過程で、違いが出たものと考えられます・・。アタックが甘くマイルドで、“コシ”に艶が感じられ、甘美で芳醇なサスティンは倍音成分が衰えることがなく、ハイ・ノ-トの囁くようなピアニッシモが会場の隅々まで鳴り響くまでには、大変な苦労があったことは言うまでもないでしょう・・。しかし、こうした楽器が西洋で称讃されるに到る前には、“硬くて大きな持続しなくていい音なら簡単に出せる”ということを奏者、聴衆共に知っていたことになり、その方が脅威なのです(^^;)・・・。
【ピックアップの名器】
一方ピックアップでは、“ダラダラ伸びる低い音なら簡単に出せる”ので、寧ろ高域特性の素晴らしいものは珍重されます。
◆高音が良く出るピックアップにするには?インダクタンスを低く磁力を強くすればいいです♪◆
このことは一見、大きなコイルと磁力の強いマグネットを組み合せると、パワ-と高音のバランスが保たれるようですがそうではありません。この方法では高域の減少を完全に防ぐことはできないのです(^^;)・・。加えて、磁力が強過ぎると弦を引き寄せてしまい、振動に悪影響を及ぼします。また六角ポ-ルピ-スなどを介して磁束を伝導し、収束させて弦に当てる方法をとっても、弦振動に反応する磁界の幅(マグネティック・ウインドウと呼ぶ)が変ってしまい、磁束の変化が断続した状態になるため、セラミック・マグネットの時もそう言われますが、陶器的な“脆い”音質になりやすいです。
ピル=ロ-レンス はこの、高音も良く出てパワ-が大きく、磁力が弱く、マグネティック・ウインドウが途切れないという困難な問題を、空芯コイルを使って奇跡的に解決しました♪空芯コイルにすれば直流抵抗は8KΩでも、インピ-ダンスは8.2KΩしかないピックアップを作ることも可能なのです。(直流抵抗に関わりなく高域特性が素晴らしいです)。細長いバ-・ポ-ルピ-スで弦振動を感知するこのピックアップは磁力を弱くしても高音とパワ-が保たれるのが特徴で、弦を引き寄せてしまい、振動に悪影響を及ぼすということがありません・・。
ロ-レンス のピックアップは磁界の幅が細いイメ-ジから、「クリア-なサウンドと薄っぺらなサウンドを混同している」と評されることもありますが、“ハムバッカ-なら2本で拾う”ので問題ないでしょう。要はバランスなのです♪・・・。
【弓とディスト-ション】
ヴァイオリンでは弓を使ってアタックの連続のような音が出せるので、メイプルの鋭過ぎるアタックと平板で綺麗過ぎるサスティンが不連続になってしまう欠点は、長い間目立つことがありませんでした。
ギタ-にディスト-ションをかけても、その弓と同様の作用をして、アタックとサスティンの繋がりの悪さをカヴァ-してしまいます。・・が、その代償として、ちょっと“コ-ドを高度に”しても音が濁るようになったことは、ギタ-音楽が舗装路を飛ばす快感を忘れてしまい、こうした曲を避けるようになった点ではマイナスでした・・。
“可能な限り和音の連結をスム-スにしようとすれば?自然に高度なコ-ドを経ようとする”ということがあって、これは“可能な限り速く、安全に、そして快適にAから目標のBへ移動しようとすれば?自然に舗装路を経ようとする”ということと同じだからです。
またプロの観点は、「“日曜”に悪路を走破したい。目標というより勝てばいいんでしょ?」になりやすい教育性評価基準がまかり通っていることに対して、『音楽はそれほど“日曜”になってしまったのだろうか('.'
?)。それに、普段の約束を守って来たから次の仕事があっただけなのに・・。』などと思います(^^;)・・・。
【樹脂ネック】
そのヴァイオリン効果をギタ-で生音だけで再現する難しさを、科学的に説明すると、『剛性が忠実な描写と延いては“コシ”の滑らかさに貢献し、軽量化がタイトな低音をもたらす・・。しかし、剛性を上げようとすると大抵の素材は重くなってしまい、鳴り切るまでに時間がかかり、特に伝達に時間を要す低音の出遅れが目立つようになる。この要素は、単なる軽量化では重低音は出ないところからワイドレンジに感じられる面も持っているが、結局、“コシが伸びた”ことにはならない。』ということになります(^^;)。
しかし諦めた訳ではありません!ギタ-、エレクトリック・ベ-スでは、生音でも“枯れたコシの部分が伸展する新しいネック素材”というのを今も捜し続けているのです。Pau
FerroやIronwoodといった、世界一堅い木が話題になったこともありました♪
因みにグラファイトネックにした場合は、アタックはツルンとし過ぎていて物足りなさはありますが、余りアタックとサスティンの境目を感じなくなった一方で・・、サスティンの収束もアルミネックなどに比べてずっと適度で好ましいです♪ただ、樹脂で固めていることに変りはないのか?Recorder(リコ-ダ-)に似た音色になってしまうようです(笑)・・・。
【最新情報~Ovangkol Neck~】
WarwickのOvangkol Neckには衝撃を受けました!
① WarwickのStreamer Jazzman Flamed
Maple-Swamp Ash Body Ovangkol Neck(Cedric
A.Napoleon使用)
のOvangkol Neckは、多分ブリッジ構造にも負うところが多いのでしょうけど、Mapleのガラス質の音もすればAshのコリコリした音もする。Alder風の枯れた音も出せる。ドイツらしい実に多彩な音がしていて・・、【ヴァイオリンの名器】の所で触れた同じくドイツのカ-ル・シュタイナ-とは一体どういう楽器だったか?シュタイナ-はストラディヴァリの影に隠れて余り取り上げられることこそありませんが、一度聴いてみたい気持ちにさせられました♪
② WarwickのCorvette Proline Flamed Maple
Body Ovangkol Neck(P-nut使用)
のOvangkol Neckと、
③ WarwickのStreamer Stage I Flamed Maple
Body Maple Neck(Limp Bizkitで使用)
のMaple Neckを聴き比べてみますと、Maple
Neckにした物は艶が出過ぎていたことがわかります。Ovangkol
Neckを聴いた後ではそれ位、グラファイトネックさえMaple
Neckに近い“透明過ぎて不明瞭な音”に聞えてしまうから不思議です。
④ FoderaのLincoin Goines's Imperial 5 Koa
Body Koa-Ash Neck
のKoa-Ash Neckでは、『もうちょっとツルンとしてもいいかな?』と思う反面、ちょっぴり枯れた、随分輪郭のはっきりしたAlderのような音が好印象でした。
もっとも、CDの高域は元々ザラ付いているので、これ以上艶があってもわからないかも知れませんが・・。
∴ WarwickのCorvette FNA Jazzman Flamed
Maple-Swamp Ash Body Ovangkol Neck(使用ベ-シスト不明)
の新しいOvangkol Neckは、薄くWalnutが挟んである以外は殆ど①のStreamer
Jazzmanと同じ材質です♪違うのはボディ形状ですが、まだ音が聴けなかったため・・、では、Flamed
Maple Body同士ですが、②のColvetteボディと③のStreamerボディではどうか?をOvangkol
NeckとMaple Neckの違いは聴かないようにして聴き比べてみることにしました。その結果は、材質が同じなら、Corvetteボディの方が鳴っているように、Cedric
A.Napoleonに逆らうのは大変ですが(笑)私には感じられました。
これらはエレクトリック・ベ-ス市場での新しい動きです・・。評論家はウェスやジミヘンを誉める余り、オクタ-ヴ奏法をしないギタ-やディスト-ションのかかっていない時代のギタ-を「まだこんなことをしていた」のように書くのですが、しかしそれでは生音を評価したことにはならないのです(^^;)。アンプで加工してそうなるようにするギタリストは、益々ギタ-本体はオ-ルドのままがいいと思うようになって行き、『ギタリストは保守的』と言われ、一方のギタ-市場が相変らずなのはそのためだと考えられます・・・。⌒♪

|
┗━♪⌒Gary
Mooreの CHARVEL ストラト !ブリッジは
SCHECTER の駒(ブラス製)を乗せた CHARVEL製
肉厚ブラスブリッジに、ア-ムはスティ-ル製。ブラス・ピックガ-ド。パドックボディ、バ-ズアイ
メイプルネックに、ペグはプラスティック・ノブで軽量化した
Schaller 。ピックアップはフロントが
ディマジオ・パフ 、リアが
ディマジオ・X2N 。
このサイトが“f”サウンドホ-ル
デザインのア-チドトップ フルアコ-スティックボディ中心に書かれているのは、第一に太いアタックを追求する、ジャズ・ギタ-の需要で選んでいるからです。応用すれば、ディスト-ションの需要で選ぶことも可能で、要はエッジ(“頭”)を際立たせた方が綺麗にかかるんですから、ソリッドを前面に出すこともあります(笑)・・。このような“アタックが細い方がいいソリッドでも、濁りのない太いアタック音を出せるように、質量の割に低域の反応が早いブラス製サスティンプレ-トを入れていた着想”を語っていたのは、'84年のサンタナ自身でした。'81年のカルロス・サンタナVS高中
正義の時のSantanaの YAMAHA SG のことです。市販品では上級機種には設定されておらず、SG-2000
、SG-2000MT のみでした。
ゲイリ-・ム-アはこのアイディアを更に推し進め、ディスト-ションを考慮した中では究極の名器を作っています♪それが'82年のプレイヤ-別冊に載ったこのギタ-です。ディスト-ションを汚すアタックの太さは、極力肉厚ブラス・パ-ツの、優れた音伝達でアタックの低域(パンチ)を増し、温かく拡がる音でコシを伸ばして出すというこの野心作は、パドックの、“減衰してディスト-ションがかからなくなっても擦弦楽器のようなザラつき感が残る余韻”との繋がりも見事で、'83年のRockin'
Every Nightが、長い試聴歴の中でも特に思い出されます♪
レス・ポ-ル
属の、ネックをマホガニ-にして太くし、メイプルトップで明瞭さを出す設計思想ではこうはならなかったでしょう・・。生ではさすがにパドック材のトレブリ-な“頭”が鋭過ぎましたが、ピックアップの磁界を広くしてなだらかに拾おうにも
X2N が頂点の選択であり、肉厚ブラスブリッジにも踏み切れない人が多い今日、ストラト
属がアッシュボディでバランスを取る方向へ戻るのは、当然の成行きでした・・・。⌒♪>'04/9/6∈
|
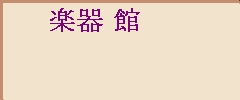
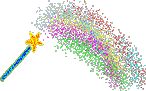 ~*☆。.'゚★。、::。.::-…・ ・☆
~*☆。.'゚★。、::。.::-…・ ・☆